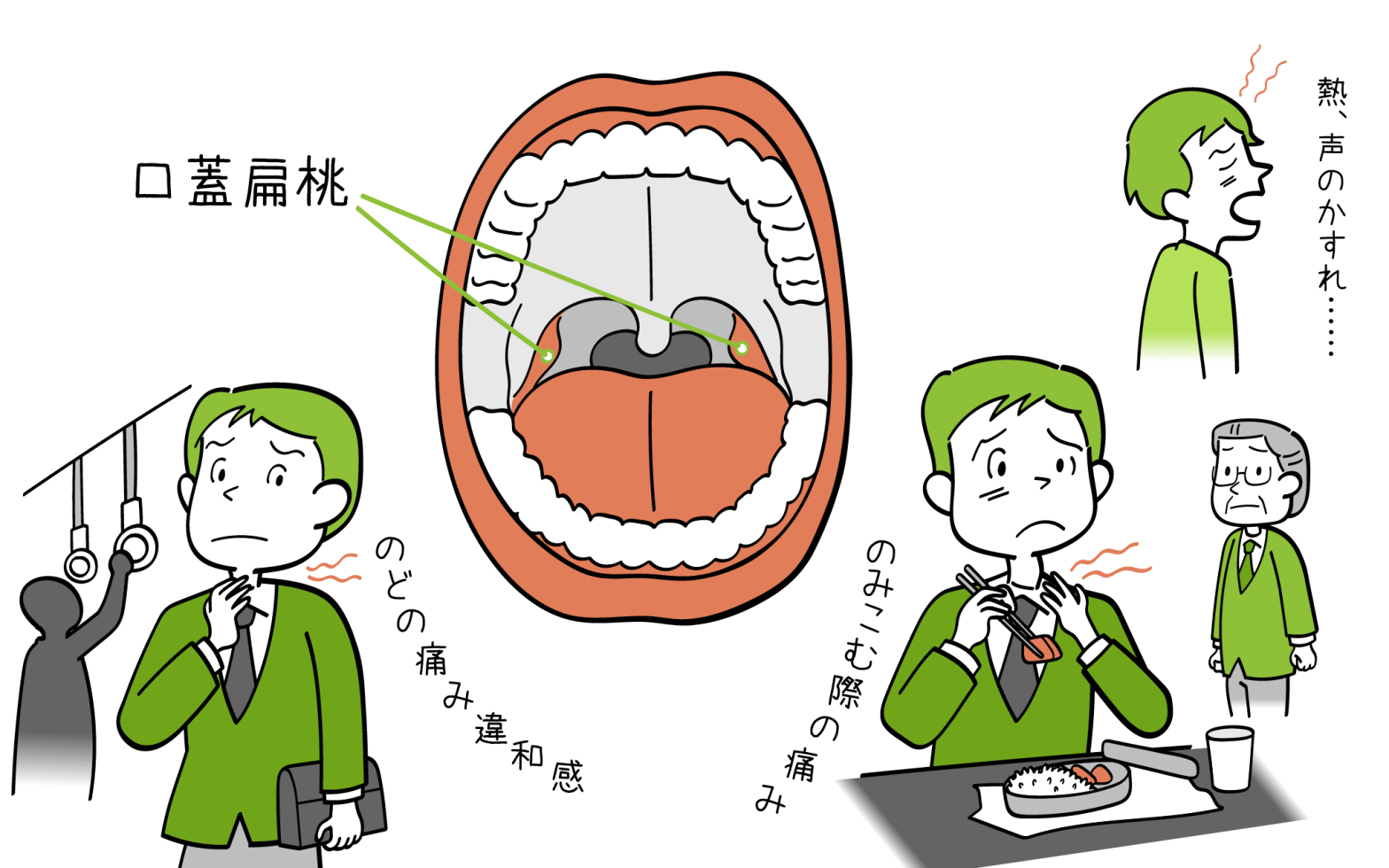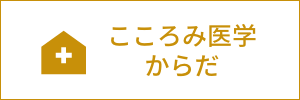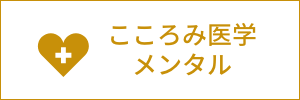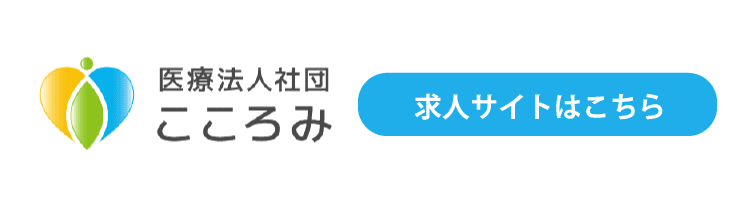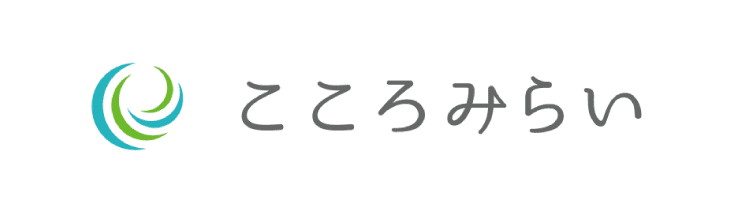糖尿病に合併した高血圧のリスク・治療をガイドラインに沿って解説
糖尿病は、高血圧を合併しやすい病気です。
本記事では、糖尿病に合併した高血圧のリスク、糖尿病で高血圧になるメカニズム、糖尿病に合併した高血圧の治療について解説します。
これを読めば、糖尿病に合併した高血圧の概要が分かります。
糖尿病を治療する際に役立ててみてください。
1. 糖尿病に合併した高血圧のリスク
糖尿病に合併した高血圧は、糖尿病による大血管症、細小血管症を発症するリスクファクターです。
1-1. 大血管症のリスクファクター
糖尿病に合併した高血圧は、動脈硬化による大血管症(冠動脈疾患、脳血管障害、末梢動脈疾患)の重大なリスクファクターです。
糖尿病では血圧が高いほど、大血管症による死亡リスクが高くなります。
収縮期血圧が10mmHg上昇するにつれて、大血管症による死亡率が18%上昇するという報告があります。
1-2. 細小血管症のリスクファクター
糖尿病に合併した高血圧は、糖尿病性神経障害、網膜症、腎症などの細小血管症のリスクファクターです。
1-2-1. 1型糖尿病で神経障害を引き起こす
1型糖尿病では、高血圧は神経障害を起こす最も大きな原因です(リスクが4.1倍)。
2型糖尿病では、高血圧と神経障害の関連は明確ではありません。
1-2-2. 糖尿病網膜症を進行させる
1型糖尿病において、収縮期血圧が10mmHg上昇すると糖尿病性網膜症のリスクが14%上昇するという報告があります。
2型糖尿病において、収縮期血圧が17mmHg低下すると糖尿病性網膜症の消失が20%増加し、拡張期血圧が10mmHg上昇すると非増殖性網膜症の出現するリスクが87%増加したという報告があります。
1-2-3. 糖尿病性腎症の重大な危険因子となる
血圧のコントロールは、糖尿病性腎症の発症・進行抑制に有効です。
1型糖尿病では、腎症の進行に伴って高血圧の合併が増加すると考えられています。
2型糖尿病では、高血圧の合併が腎症に先行すると考えられています。
慢性腎疾患の進行にともない高血圧の合併が増え、大多数の末期の腎不全では高血圧を合併します。
2. 糖尿病で高血圧になるメカニズム
糖尿病で高血圧を発症するメカニズムとして、インスリン抵抗性が重要な役割を占めます。
2型糖尿病でみられるインスリン抵抗性は、高インスリン血症を引き起こします。
高インスリン血症は、以下のメカニズムにより、循環血漿量および末梢血管抵抗を増加させて血圧を上昇させます。
- 腎臓からのナトリウムの再吸収を促す
- 血管平滑筋細胞内のナトリウム・カルシウム濃度を上昇させる
- 交感神経の活動を亢進させる
- 血管平滑筋の細胞を増殖・肥大させる
- レニン・アンジオテンシン系を亢進させる
3. 糖尿病に合併した高血圧の治療
心血管イベントおよび脳卒中の発症を予防するため、診察室血圧 130/80mmHg未満を目標とした降圧療法が推奨されます。
3-1. 治療計画
- 微量アルブミン尿またはタンパク尿
a.あり→ARBまたはACE阻害薬
b.なし→ ARBまたはACE阻害薬、Ca拮抗薬、利尿薬 - 1で効果が不十分な場合、用量を増加または2剤を併用
- 2で効果が不十分な場合、 ARBまたはACE阻害薬、Ca拮抗薬、利尿薬の3剤を併用
3-2. 食事療法
肥満を伴う糖尿病において、総エネルギー摂取量を適正化することにより、インスリン作用からみた需要と供給のバランスをとって、高血糖を改善します。
肥満の解消によりインスリン抵抗性を是正すれば、 高血圧ならびに心血管疾患のリスク因子が改善します。
このために5%以上の体重減少が必要です。
3-3, 運動療法
糖尿病および高血圧を改善するために、有酸素運動とレジスタンス運動が有効です。
血糖値がコントロールされ、血圧が低下し、心血管疾患のリスクファクターが改善されます。
また生活の質(QOL)の改善にもつながります。
開始前に運動制限の必要性の検討が必要です 。
中強度の有酸素運動を週150分以上、週に3回以上、運動をしない日が2日以上続かないようにしてください。
レジスタンス運動は間隔を空けて週に2~3回行うことが望まれます。
4. まとめ
糖尿病に合併した高血圧は、糖尿病による大血管症、細小血管症を発症するリスクファクターです。
糖尿病で高血圧を発症するメカニズムとして、インスリン抵抗性が重要な役割を占めます。
心血管イベントおよび脳卒中の発症を予防するため、診察室血圧 130/80mmHg未満を目標とした降圧療法が推奨されます。
【お願い】
「こころみ医学の内容」や「病状のご相談」等に関しましては、クリニックへのお電話によるお問合せは承っておりません。
診察をご希望の方は、受診される前のお願いをお読みください。
【お読みいただいた方へ】
医療法人社団こころみは、東京・神奈川でクリニックを運営しています。
「家族や友達を紹介できる医療」を大切にし、社会課題の解決を意識した事業展開をしています。
医療職はもちろんのこと、法人運営スタッフ(医療経験を問わない総合職)も随時募集しています。
(医)こころみ採用HP取材や記事転載のご依頼は、最下部にあります問い合わせフォームよりお願いします。
カテゴリー:糖尿病 投稿日:2025-05-05
関連記事

HbA1cが高いと糖尿病?HbA1cとは?
はじめに みなさんが健康診断をうけられると、血液検査の項目のひとつに「HbA1c」という値があります。 この値は、糖尿病に関係する値としてご存じの方も多いかと思います。こちらが高い場合、糖尿病の可能性があるため病院での精… 続きを読む HbA1cが高いと糖尿病?HbA1cとは?
カテゴリー:糖尿病 投稿日:
人気記事

【医師が解説】喘息の長期管理薬(吸入ステロイド)の効果と副作用
喘息の長期管理薬とは? 喘息は、気道に慢性炎症が起きて狭くなっている状態です。それが引き金となって気道が過敏になり、ちょっとしたきっかけで咳や息苦しさをくり返します。 喘息の治療は、 炎症を抑え、喘息の悪化や発作を予防す… 続きを読む 【医師が解説】喘息の長期管理薬(吸入ステロイド)の効果と副作用
カテゴリー:喘息の長期管理薬(吸入ステロイド) 投稿日: