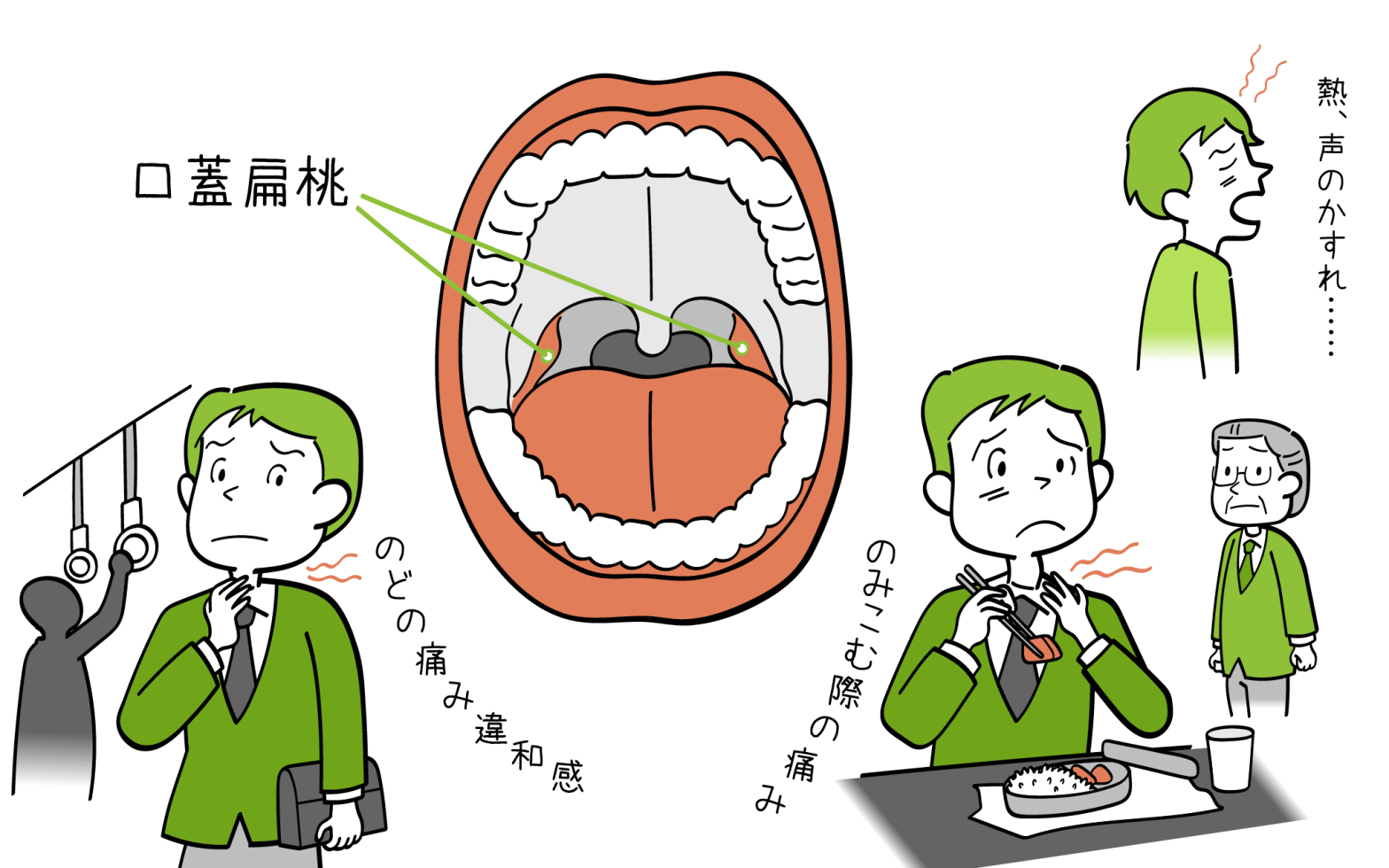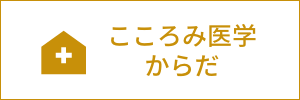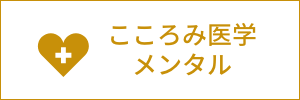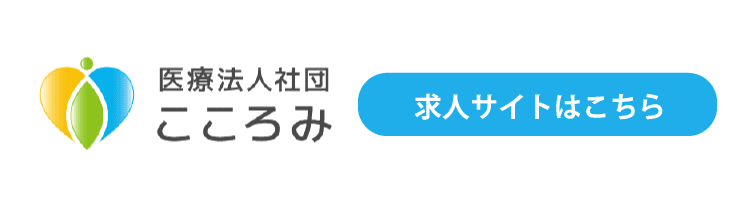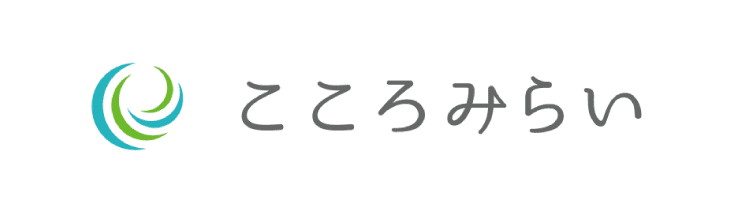子どもの便秘・下痢
子どもの便秘や下痢の訴えは、多くの保護者に経験があるのではないでしょうか?
子どもが便秘や下痢を起こすことは一般的によく知られています。
症状が便秘や下痢の単独で他に症状がない場合、緊急性は低く自然に改善することが多いですが、時には重大な疾患のサインであることもあります。
便秘と下痢は、腸内での水分吸収や腸の運動の変化により見られますが、どちらも腸の機能不全が異なる形で現れたものです。
今回は、便秘や下痢の原因疾患、そして緊急性の高い状況とその対策について詳しく解説します。
腸の役割と、便秘と下痢の原因
便秘や下痢の原因を解説する前に、まずは腸の役割について知っておきましょう。
腸の役割|水分と栄養の吸収
腸は消化器系の一部であり、栄養素や水分を吸収する重要な役割を果たしています。
小腸では主に栄養素と一部の水分が吸収され、大腸ではさらに水分が吸収されることで便を固めて形作る役割を果たします。
小腸も大腸も、蠕動運動(ぜんどううんどう)という腸自体の運動で、食物の塊を送り出しています。
便秘と下痢の原因
腸がうまく機能しないことで便秘や下痢を起こすのですが、その理由について解説します。
便秘や下痢を起こす原因には以下の3つがあります。
- 腸の蠕動運動の変化
- 水分吸収の過剰または不足
- 食事や生活習慣の影響
①腸の蠕動運動の変化
蠕動運動(ぜんどううんどう)とは、消化管の筋肉がリズミカルに収縮と弛緩を繰り返すことで、消化管の中にある塊を口側から肛門側へと送り出す運動です。
小腸や大腸でこの蠕動運動が正しく行われることで、栄養素の吸収や便の形成・排出がスムーズに行われます。
この蠕動運動が早くなると、内容物の水分を腸が十分に吸収できないまま腸内を通過してしまうことになるので、水分を多く含んだ便=下痢になります。
逆に、蠕動運動が遅くなると、腸内に長く留まることになるので水分が過剰に吸収されます。
そうすると、便が硬くなるので排便が困難になり、便秘となります。
②水分吸収の過剰または不足
消化管内には、食べ物と一緒に飲んだ水分や、消化液として分泌された水分が存在します。
これらの水分が小腸と大腸で吸収されることで、体内の水分バランスは保たれています。
腸の水分吸収の程度は、腸の蠕動運動以外の要因でも変わります。
例えば、腸壁に感染症や炎症があると、腸の水分吸収能力が低下するので腸管内に過剰に水分が残ることになります。
また、乳糖不耐症で見られるように糖類のような浸透圧の高い(濃い)ものが分解されないまま腸管内に送り出されると、体は腸管内の濃度(浸透圧)を下げようと、腸管内に水分を引き込みます。
このような原因から腸管内に水分が多く残ってしまうと、水分の多い柔らかい便や下痢という形になります。
③食事や生活習慣の影響
便秘や下痢には、食事や生活習慣も大きな影響を与えます。
例えば、水分不足や繊維不足は便秘の原因になりやすく、脂っこい食事や消化しにくい食べ物は下痢になりやすいとされています。
便通と食事・生活習慣の影響は様々なところで言われているので、ここでは簡単な解説にしておきます。
体内で水分不足が起こると、体は大腸で水分を過剰に吸収しようとします。
その結果、便が硬くなり排出されにくくなります。
また、食物繊維は腸管内で便のかさを増やし、腸蠕動運動を刺激します。
したがって食物繊維が不足すると、便の量が減り硬くなるので便秘気味になります。
脂っこい食事や消化しにくい食べ物は下痢の原因になることが多いです。
その理由は消化不良のまま脂肪分などが腸に到達すると、浸透圧を上げたり、脂肪分が腸蠕動を刺激し亢進させたりするからです。
生活習慣においては、運動不足やストレスが便通に影響を与えます。
運動不足は腸蠕動の動きを低下させ、ストレスは自律神経の乱れを引き起こすことから、便秘になりやすいと言われています。
緊急性が高い症状
便秘や下痢はほとんどの場合軽度で自然に治ることが多いですが、以下の症状がある場合は緊急性が高いと考えられ、すぐに医療機関を受診する必要があります。
【緊急性が高い症状】
- 激しい腹痛:突然強い腹痛が発生し、泣き止まない、ぐったりしている場合
- 血便:便に血が混ざっている、またはイチゴゼリー状の血便が見られる場合
- 嘔吐を伴う腹痛:嘔吐が頻繁に起こる、腹痛を伴う場合
- 持続する下痢・便秘:下痢や便秘が数日以上続く、水分補給が難しい場合
発熱・体重減少を伴う便秘や下痢:発熱や体重減少が見られる場合は、感染症や重大な疾患の可能性があります。
便秘や下痢を起こす疾患
便秘と下痢は、腸の蠕動運動の変化や水分吸収の異常、そして生活習慣や食事の影響によって引き起こされるのですが、以下では疾患として便秘や下痢を引き起こすものを解説します。
機能性便秘
機能性便秘は最も一般的な便秘の原因で、子どもの便秘の約90%以上が機能性便秘と考えられています。
特定の病気というわけではなく、排便習慣の乱れや、生活習慣や心理的な要因が原因とされています。
【主な原因】
- トイレを我慢するなどの排便習慣の乱れ
- 食物繊維や水分の不足、偏食などの食生活の問題
- 運動不足
乳糖不耐症
乳糖不耐症とは、乳糖を分解するラクターゼという酵素が無い、もしくは働きが弱いことで起こる症状全般を指します。
- 症状:下痢、お腹の張り、腹痛、嘔吐、酸性便(酸っぱい匂いの便)など
乳糖とは、主に牛乳や母乳などの乳製品に含まれている糖質の種類で、ラクターゼという酵素によって分解されます。
乳糖不耐症では濃度の高い乳糖が分解されないまま腸管内に入ってくるので、それを薄めようと腸管内に水分が引き込まれ、下痢になります。
「乳製品を食べると、お腹がゆるくなる、お腹が痛くなる」という場合は、乳糖不耐症の可能性が考えられるでしょう。
乳糖不耐症の原因には、生まれつきラクターゼの生産量が少ない先天性のものや、小腸の炎症や感染症などによって生じる後天性のものなどがあります。
症状の軽減には、乳製品の摂取を控える、分解酵素を補うサプリメントを使用することが有効とされています。
食物アレルギー
食物アレルギーの反応の1つとして、便秘や下痢などの消化器症状が現れることがあります。
- 症状:便秘や下痢、腹痛、発疹・かゆみ、咳・息苦しさなど
アレルギー反応を起こす食品(アレルゲン)を摂取すると、体の免疫システムが過剰に反応します。
その反応は腸管にも及び、腸の粘膜が炎症を起こし、腸の動きや水分吸収に影響を与えます。
このようなことから、便秘や下痢といった症状が起こります。
まずはアレルゲンとなる食物を特定し、それらを回避するか除去した食事を摂取するようにしましょう。
食物アレルギーで便秘になった場合は、食物繊維や水分を増やし、下痢になった場合は、水分を補給し消化しやすい食事を摂るように心がけましょう。
薬剤性(薬剤性便秘/薬剤性下痢)
薬剤性便秘と薬剤性下痢は、薬の摂取が原因で起こる便秘や下痢のことを指します。
特に子どもは体が小さく、薬の影響を受けやすいので、薬の副作用としてよく見られる症状です。
薬が体内で作用する過程で、腸の動きや水分のバランスに影響を与えることで発生します。
【薬剤性便秘】
一部の子どもが服用する薬によって起こるため、全体としてはあまり多くありません。
薬の摂取開始と便秘のタイミングが一致します。
- 原因となる薬:抗てんかん薬、抗ヒスタミン薬、カルシウムや鉄剤など
【薬剤性下痢】
薬剤性の下痢は、抗生物質などを服用した際に見られる下痢です。
抗生物質は腸内の善玉菌も殺してしまうため、腸内環境が乱れて下痢になることがあります。
- 原因となる薬剤:抗生物質、マグネシウムを含む下剤など
薬剤性便秘の場合、便が出にくい場合は、食物繊維を多く含む食事を心がける、水分をしっかり摂る、軽い運動を取り入れることが効果的です。
薬剤性下痢の場合、水分補給をしっかり行い、体が脱水状態になるのを防ぐことが大切です。
また、プロバイオティクス(善玉菌を増やすもの:乳酸菌・ビフィズス菌、発酵食品など)を摂取すると、腸内環境を改善する助けになる場合もあります。
薬剤性の便秘・下痢の場合は、医師に相談しましょう。
薬の服用を継続すべきかどうか、減量・他の薬への変更なども含めて検討してもらうと良いでしょう。
食中毒
細菌・ウイルス・寄生虫などの病原体や、これらの病原体が産生した毒素を含む食品などを摂取することによって起こる、急性の消化器疾患です。
夏を中心に発生します。
- 症状:激しい下痢や嘔吐、発熱、腹痛
食品と一緒に摂取した病原体や毒素が腸を刺激して、腸の粘膜が炎症を起こします。
炎症を起こした腸は水分の吸収が正常に行われなくなります。
また、産生された毒素が腸内に水分を過剰に引き込むことがあり、これらの理由によって下痢が起こります。
食中毒の治療は基本的に経過観察となります。
下痢や嘔吐は、病原菌やその毒素を体外に排出しようとする防御反応です。
病原菌や毒素が体外に排出されると食中毒による症状は落ち着いてきます。
腸閉塞(イレウス)
腸閉塞とは、腸が物理的に詰まったり、ねじれたりして、食べ物やガスが通らなくなる状態のことを指します。
腸閉塞で見られる腹部症状は、緊急性の高い症状で、急性腹症にも該当します。
急性腹症とは、突然発生する強い腹痛のことで、腹痛以外にも嘔吐・発熱・下痢や便秘などを伴います。
急性腹症を放置すると、命に関わるリスクもあるため緊急の対応が求められます。
- 症状:腹痛、嘔吐、腹部の膨満、便秘、ガスが出なくなる
子どもの腸閉塞を起こす原因の中で、最も多いものとされているのが「腸重積」です(腸重積に関する解説は後述します)。
その他にも生まれつき腸の一部が閉じている「先天性腸閉鎖症」や、新生児〜乳幼児に起こりやすいとされる「腸捻転」などがあります。
治療としては、保存的治療(絶食・点滴治療)、外科的治療(手術)があります。
腸重積に対しては「高圧浣腸」という治療方法があります。
腸重積
腸重積は生後6ヶ月から2歳くらいの子どもに多く見られ、腸閉塞を起こす原因で特に多い疾患とされています。
腸重積も急性腹症に該当する疾患で、緊急の治療が必要となる代表的な疾患になります。
小さい子どもや乳児の場合は、症状を言葉で伝えられないので、泣き方やぐったりしている様子から症状を認識する必要があります。
- 症状:断続的な腹痛、イチゴゼリー状血便、嘔吐

(一般社団法人日本小児外科学会)
腸重積とは、腸の一部が隣り合う腸管の中に入り込んでしまう状態のことで、腸が二重に重なり合うことで様々な症状を引き起こします。
具体的には、腸管の通り道が塞がれる、血流が阻害され腸管が壊死(損傷)を引き起こすなどがあります。
腸管が塞がれるので便秘になりますが、それよりも突然の激しい腹痛や、腸管が圧迫され腸への血流が途絶えることの方が重大です。
便は出ませんが、腸の粘膜が傷つき血液が漏れ出ることから、血液の混ざったイチゴゼリー状の粘液便が出ることがあります。
発症から経過が短く、腸管への血流遮断が認められない場合には「高圧浣腸」という治療を行います。
腸管の壊死(損傷)が認められる場合や、高圧浣腸で腸の重なりが解除できない場合には、緊急で外科的手術を行う必要があります。
感染性胃腸炎
感染性胃腸炎の主な原因として多く見られるのが、ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルスへの感染です。
特にノロウイルスとロタウイルスは、感染力が非常に強く、少量のウイルスでも感染が成立するため、子どもの集団生活の場(幼稚園、学校など)で流行しやすい病原体です。
- 症状:下痢、嘔吐、発熱、腹痛
ノロウイルスは生牡蠣や海産物に付着していることが多く、食中毒の原因にもなります。
感染性胃腸炎の中に食中毒も含まれる形にはなりますが、感染経路が食べ物や飲み物に限定されておらず、接触感染や空気感染でも感染が成立する点で、食中毒よりも範囲は広いと考えられます。
ノロウイルスやロタウイルスは食中毒としての感染よりも、感染者から排泄された便を介した接触感染や空気感染の方が頻度としては多いと言われています。
【お願い】
「こころみ医学の内容」や「病状のご相談」等に関しましては、クリニックへのお電話によるお問合せは承っておりません。
診察をご希望の方は、受診される前のお願いをお読みください。
【お読みいただいた方へ】
医療法人社団こころみは、東京・神奈川でクリニックを運営しています。
「家族や友達を紹介できる医療」を大切にし、社会課題の解決を意識した事業展開をしています。
医療職はもちろんのこと、法人運営スタッフ(医療経験を問わない総合職)も随時募集しています。
(医)こころみ採用HP取材や記事転載のご依頼は、最下部にあります問い合わせフォームよりお願いします。
カテゴリー:よくある子供の症状 投稿日:2025-05-05
関連記事
人気記事

【医師が解説】喘息の長期管理薬(吸入ステロイド)の効果と副作用
喘息の長期管理薬とは? 喘息は、気道に慢性炎症が起きて狭くなっている状態です。それが引き金となって気道が過敏になり、ちょっとしたきっかけで咳や息苦しさをくり返します。 喘息の治療は、 炎症を抑え、喘息の悪化や発作を予防す… 続きを読む 【医師が解説】喘息の長期管理薬(吸入ステロイド)の効果と副作用
カテゴリー:喘息の長期管理薬(吸入ステロイド) 投稿日: