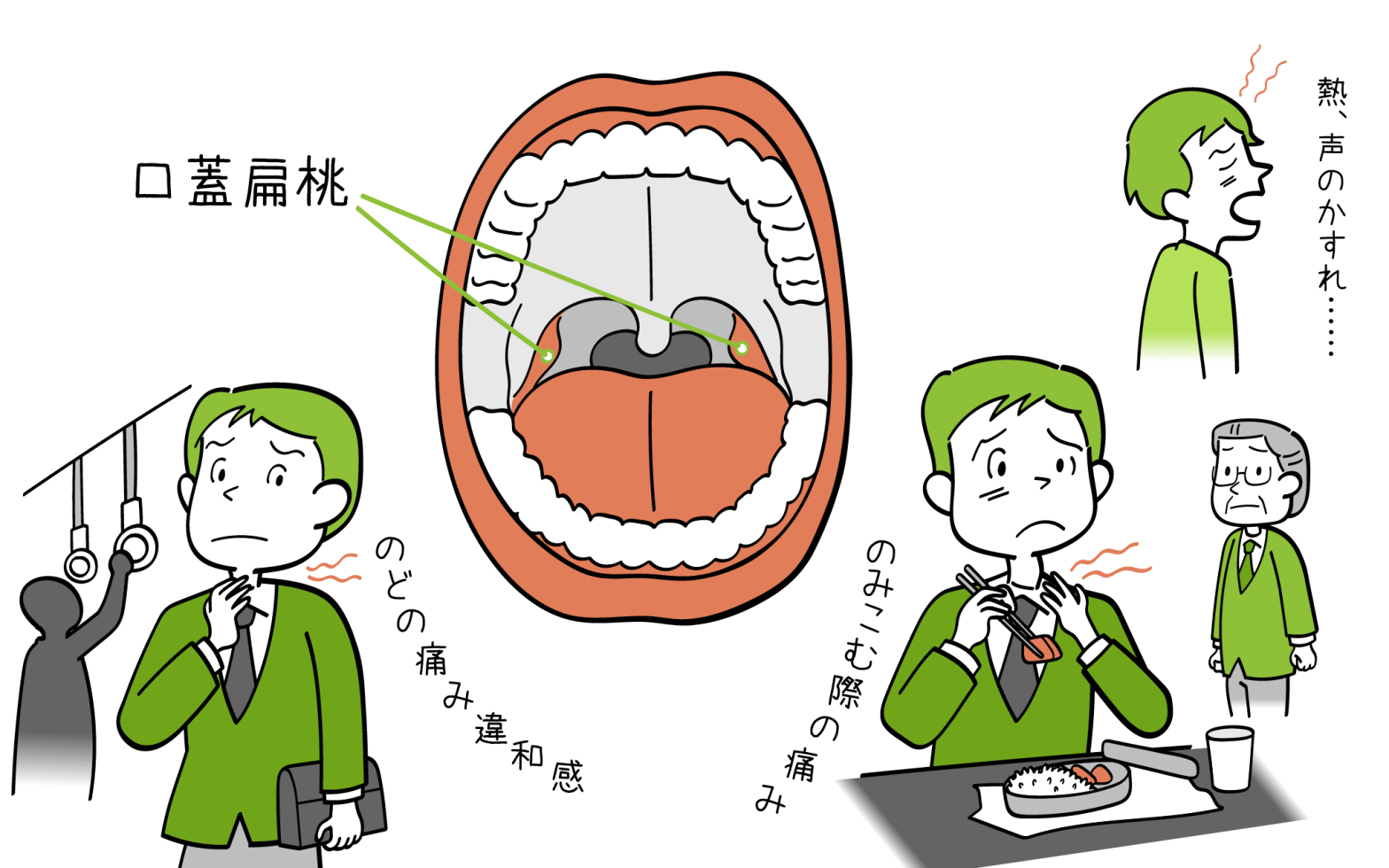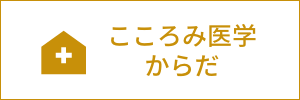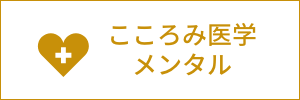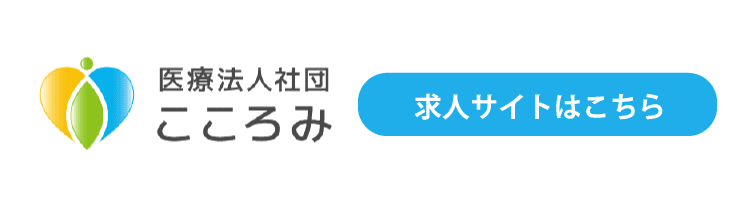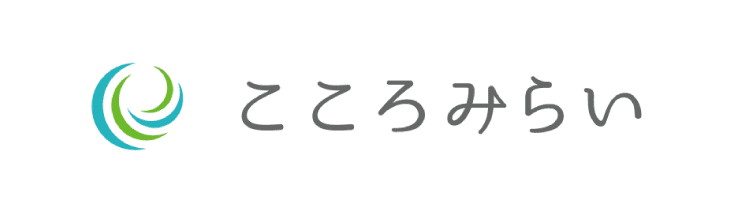生後2か月の赤ちゃんに必要な予防接種と、同時接種のススメ
赤ちゃんはママからもらった免疫によってたくさんの感染症から守られていますが、その効果は少しずつ弱まってしまいます。
予防接種は、VPD(ワクチンで防げる病気)から赤ちゃんを守るために、欠かせないものです。
赤ちゃん自身の免疫を育てるために、生後2ヶ月を迎えたら予防接種を開始しましょう。
※VPD: Vaccine Preventable Diseases ワクチンで予防可能な病気や感染症の総称

予防接種を効率的に行うためには同時接種がおすすめ
生後2ヶ月に接種できるワクチンは、小児用肺炎球菌ワクチン、5種混合ワクチン、B型肝炎ワクチン、ロタウイルスワクチンの4種類です。
これらのワクチンは、赤ちゃんの免疫をしっかり育て、持続性を持たせるために、2〜3回繰り返して行う必要があります。
0歳のうちに受ける予防接種は10回以上。
推奨される期間内に接種を完了し、早期に免疫を獲得するには、同時接種が最適な方法です。

同時接種の安全性について
同時接種は、1回の通院で数種類のワクチンを接種する方法です。
多くのママが心配するのは同時接種の安全性ですが、効果や安全性は単独接種と変わりません。
諸外国では、同時接種は長年にわたって一般的な医療行為として行われており、世界中で広く実施されている方法です。
ワクチンをひとつずつ受ける選択も可能です。
ただし、ひとつずつ受ける場合は期間内に全てのワクチン接種を完了させることが難しくなります。
予防接種に遅れが生じると、赤ちゃんをVPD(ワクチンで防げる病気)から守るという本来の目的を果たすことができません。
同時接種は、早期に確実な免疫をつけるために必要です。
同時接種するワクチンの本数に上限はありません。
注射する際は、右腕、左腕、右太もも、左太ももなど、体の異なる部位に行うのが一般的です。
何本もの注射を受ける我が子を見るのは保護者にとって心が痛みますよね。
でも、接種した日から免疫がつきはじめることや、医療機関に行く回数が減ることを考えれば、同時接種には大きなメリットがあると言えるでしょう。

小児用肺炎球菌ワクチンについて
肺炎球菌による感染症を防ぎます。
感染すると、細菌性の中耳炎や髄膜炎(脳の周りの膜の感染)、肺炎、菌血症(血液中の感染)などの病気を引き起こすことがあります。
乳幼児は重症化しやすいためワクチンによる予防が大切です。
| 接種間隔 | 初回接種 : 生後2ヶ月から可能 2回目の接種 : 初回接種から27日以上間隔をあけて行う 3回目の接種 : 2回目の接種から27日以上間隔をあけて行う 4回目の接種(追加接種): 生後12か月〜15か月の間に行う |
|---|---|
| ワクチンの種類 | 不活化ワクチン |
| 接種方法 | 13価:皮下注射 15価:皮下注射または筋肉注射 |
| ポイント | B型肝炎、5種混合、ロタウイルスワクチンと同時接種できます |
5種混合ワクチンについて
5種混合ワクチンは、5つの異なる感染症を予防するためのワクチンです。
- ポリオ:ポリオウイルスによる感染症。血液から脳や脊髄に入り込み、運動神経細胞を損傷すると、筋力低下や麻痺が起こります。子どもがかかることが多く「小児マヒ」とも呼ばれます。
- ジフテリア:ジフテリア菌が放出する毒素により、心臓の筋肉や神経に影響を及ぼし、呼吸困難や心不全を引き起こします。
- 百日せき:百日咳菌による感染症で、激しい咳が出ます。乳幼児は重症化しやすいため注意が必要です。
- 破傷風:破傷風菌の産生する毒素によって引き起こされる感染症で、主に神経系に影響を及ぼし、高い致死率を伴います。
- Hib(ヒブ):ヘモフィルスインフルエンザ菌b型という細菌による感染症で、肺炎や敗血症、髄膜炎などの重篤な病気を引き起こすことがあります。冬に流行するインフルエンザウイルスとは別物です。
| 接種間隔 | 初回接種 : 生後2ヶ月から可能 2回目の接種 : 初回接種から27日以上間隔をあけて行う 3回目の接種 : 2回目の接種から27日以上間隔をあけて行う 4回目の接種(追加接種): 生後12か月〜15か月の間に行う |
|---|---|
| ワクチンの種類 | 不活化ワクチン |
| 接種方法 | 皮下注射または筋肉注射 |
| ポイント | 小児用肺炎球菌、B型肝炎、ロタウイルスワクチンと同時接種できます |
B型肝炎ワクチンについて
B型肝炎ウイルスによって引き起こされる肝臓の病気を防ぎます。
乳幼児が感染するとキャリア(ウイルスを体内に持っている状態)になりやすく、キャリア化し慢性肝炎を発症すると、肝硬変や肝がんになるリスクが高くなります。
| 接種間隔 | 初回接種 : 生後2ヶ月から可能 2回目の接種 : 初回接種から27日以上間隔をあけて行う 3回目の接種(追加接種): 生後7〜8ヵ月の間に行う |
|---|---|
| ワクチンの種類 | 不活化ワクチン |
| 接種方法 | 皮下注射 |
| ポイント | ・小児用肺炎球菌、5種混合、ロタウイルスワクチンと同時接種できます。 ・お母さんがB型肝炎ウイルスに感染している場合は接種スケジュールが異なります。 |
ロタウイルスワクチンについて
ロタウイルスによって引き起こされる急性胃腸炎(下痢、嘔吐、発熱など)を防ぎます。
感染力が強いこと、乳児がかかると重症化しやすいこと、ロタウイルスそのものに効く薬が無いことから、予防が重要です。
ロタリックスとロタテックの2種類があります。
| 接種間隔 | ロタリックス(1価ワクチン) 初回接種 : 生後6週から接種可能ですが、他の予防接種と合わせて生後2ヶ月に接種するのがおすすめ。 2回目の接種 : 初回接種から27日以上間隔をあけて行う。2回目の接種は生後24週までに済ませる。 ロタテック(5価ワクチン) |
|---|---|
| ワクチンの種類 | 生ワクチン |
| 接種方法 | 口から飲むシロップタイプのワクチンです。 全部飲みきれなかったり、吐き出してしまうこともありますが、少量でも飲み込めた分で効果は期待できるので、過度に心配する必要はありません。 |
| ポイント | ・生後2ヶ月を迎えたらなるべく早く接種を開始しましょう。初回の接種が生後15週以降になると、腸重積症の発症リスクが増大するため、接種できなくなります。 ・接種後の約1週間は腸重積の症状(普段と比べて機嫌は悪くないか、お腹の張りはないか、便に血が混じっていないか)に注意しましょう。 ・小児用肺炎球菌、5種混合、B型肝炎ワクチンと同時接種できます。 |

予防接種後の注意点
予防接種を受けたあと30分間は、クリニック内またはクリニックの近くで待機するよう指示されます。
これは、アナフィラキシーという重篤な副作用が現れる可能性に備えるためです。
接種後30分間で蕁麻疹や嘔吐、息苦しさなどの症状が見られなければ、普段通りに過ごして問題ありません。
ただし、帰宅してからもし赤ちゃんの顔色が悪かったり、活気がないなど、いつもと異なる様子が見られる場合には、すぐに医師の診察を受けるようにしてください。
【お願い】
「こころみ医学の内容」や「病状のご相談」等に関しましては、クリニックへのお電話によるお問合せは承っておりません。
診察をご希望の方は、受診される前のお願いをお読みください。
【お読みいただいた方へ】
医療法人社団こころみは、東京・神奈川でクリニックを運営しています。
「家族や友達を紹介できる医療」を大切にし、社会課題の解決を意識した事業展開をしています。
医療職はもちろんのこと、法人運営スタッフ(医療経験を問わない総合職)も随時募集しています。
(医)こころみ採用HP取材や記事転載のご依頼は、最下部にあります問い合わせフォームよりお願いします。
カテゴリー:こどものワクチン 投稿日:2024-12-16
関連記事
人気記事

【医師が解説】喘息の長期管理薬(吸入ステロイド)の効果と副作用
喘息の長期管理薬とは? 喘息は、気道に慢性炎症が起きて狭くなっている状態です。それが引き金となって気道が過敏になり、ちょっとしたきっかけで咳や息苦しさをくり返します。 喘息の治療は、 炎症を抑え、喘息の悪化や発作を予防す… 続きを読む 【医師が解説】喘息の長期管理薬(吸入ステロイド)の効果と副作用
カテゴリー:喘息の長期管理薬(吸入ステロイド) 投稿日: