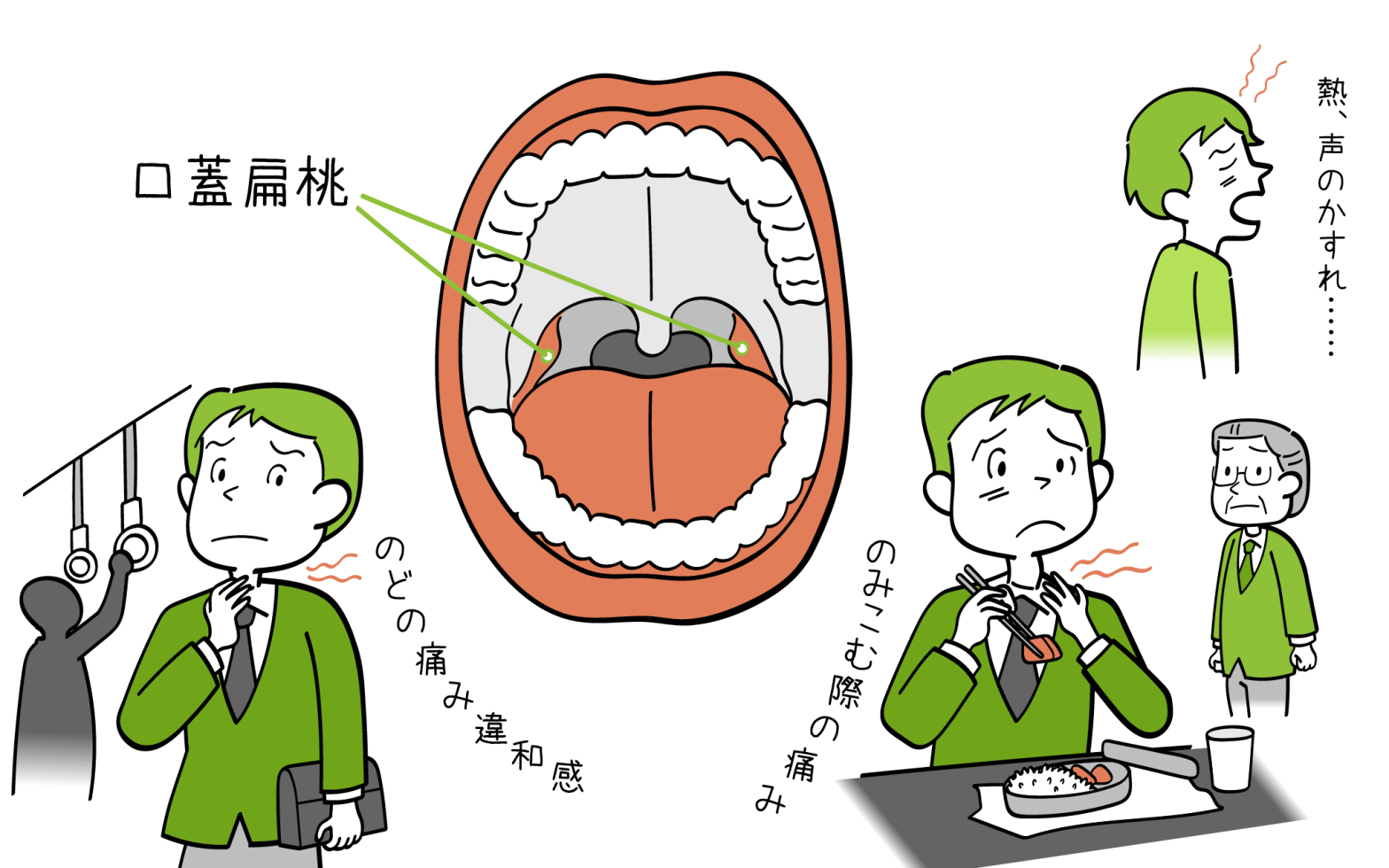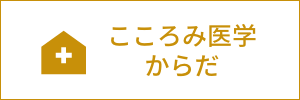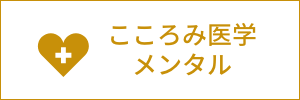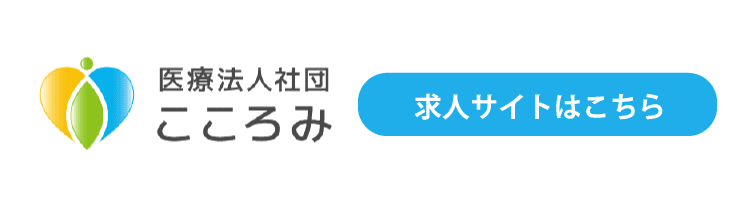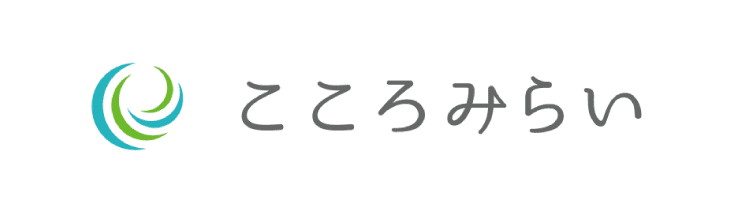糖尿病とは?
糖尿病とは、血液内の血糖値が高い状態の病気です。おそらく知らない人の方が少ないくらい、今や国民病となっています。
糖尿病は血液内で血糖があふれているため、尿から過剰な糖分が排出されます。そのため、
- 糖尿病の方の尿は、柑橘系の様な独特な臭いがある
- 糖尿病の尿にアリが群がる
などの特徴から、昔の人が糖尿病と名付けたといわれています。
しかし糖尿病の病名は知っていても、糖尿病の恐ろしさを皆さんはどれくらい知っていますか?尿から過剰な糖分が出てくる病気だけの認識だと、そこまで重症感が伝わらないかもしれません。
糖尿病の医学的な定義は、
インスリンの作用不足による慢性の高血糖状態となる病気
になります。
インスリンとは私たちの体で作られるホルモンで、血糖値を下げる効果があります。血糖値を上げるホルモンは沢山ありますが、血糖値を下げるホルモンはこのインスリンのみになります。
もともと人間をはじめとした動物は、飢餓をおそれて生存してきました。肥満が問題になっているのは、長い人類の歴史の中ではごくわずかなのです。進化の中で血糖を上げる方法はたくさん備わりましたが、下げる方法はインスリンくらいしか作られていないのです。
そのためインスリンの効果が低下すると、慢性的に血糖値が上昇し続けます。現在、予備軍も含めると、成人の6.3人に1人が糖尿病とも言われています。
1型糖尿病と2型糖尿病の違い
糖尿病は、1型と2型に分けられます。
1型糖尿病は、インスリンが膵臓にあるランゲルハンス島β細胞の破壊・消失が原因です。自己免疫および遺伝子素因が多いので、若年者に多い特殊な病態です。
一方の成人発症の2型糖尿病は、インスリン分泌低下やインスリン抵抗性をきたす素因で高血糖状態になる病気です。具体的には、
- 運動不足
- 過食(主に高脂血症)
- 肥満
- ストレス
などの環境要因が加わった病気です。主に中高年から発症する病気ですが、近年の欧米化の食事に伴い、
- インスタン食ばかり食べている
- お菓子やジュースを多く摂取している
- テレビゲームばかりで運動をほとんどしない
- 太っている
上記の特徴がある小中学生にも、2型糖尿病を認めることがしばしばあります。
このように特殊な病態ではない糖尿病は、2型糖尿病に当てはまることがほとんどです。
糖尿病の症状と合併症
ここからは、糖尿病の恐ろしさについて記載していきます。糖尿病の名前は知ってる人は多いと思いますが、糖尿病の症状について細かく知ってる人は少ないかもしれません。
「おっしこが甘くなるのでは?」くらいのご認識の方は、ぜひ糖尿病がどれだけ恐ろしい病気かを理解していただければと思います。糖尿病の恐ろしいところは、血液内に血糖があふれかえることで、全身の血管を障害することにあります。
初期であれば血糖値を正常にするために、体が無意識のうちに血糖をコントロールしようとします。その結果として、下記の様な症状が出現します。
- 口渇
- 多飲
- 多尿
- 体重減少
- 体力低下
- 空腹感
- だるさ・眠気
ただしこれらの症状で、糖尿病を心配して受診される方はほとんどいないでしょう。
糖尿病が慢性的に続き、血管が障害されると全身に症状があらわれます。特に糖尿病の世界で有名なゴロに、「シメジ」という言葉があります。
- シ・・・神経の障害
- メ・・・目の障害
- ジ・・・腎臓の障害
この3つの合併症を、糖尿病の3大合併症と言います。さらにこの順番で症状が進んでいくことが多いため、頭文字をとってシメジというのです。
それでは、糖尿病の3大合併症についてみていきましょう。
糖尿病の合併症①神経障害
神経の障害は主に細い血管からやられやすいため、末梢の神経が障害されます。
末梢の神経の中にも、
- 知覚神経・・・痛みや温度を感じる神経
- 運動神経・・・運動するように指示を伝える神経
- 自律神経・・・体温や呼吸など体の状態を自動でコントロールする神経
などに分かれます。
そのため症状として知覚神経の障害では、
- 手足のしびれや痛み
- 手足の感覚が鈍くなる
- こむら返りが起こりやすい
となります。運動神経の障害では、
- 筋力の低下
- 目がピクピクする
となります。自律神経障害では、
- ほてり
- 吐き気
- 食欲低下
- 便秘や下痢などの消化器症状
- 勃起障害
などが起こります。
しかしこれらの症状が出てきても、半分くらいの人は症状から糖尿病と気づかずに様子をみてしまいます。
糖尿病の合併症②眼の障害
末梢神経の血管が障害され続けていると、もう少し太い血管が障害され始めます。その代表が糖尿病網膜症です。
目の血管がやられることで、
- 視力低下
- 視界がぼやける
- 視野が狭くなる
などの症状が出ます。
このような症状が出現して眼科を受診することで、糖尿病が発見されることも多いです。
網膜にある毛細血管が詰まってしまうことで、酸素がうまくいきわたらなくなります。酸欠状態を改善すると新しい血管が伸びていきますが、この血管は非常にもろいです。
新生血管が破裂してしまうと眼底出血が起こってしまい、失明の原因にもなります。
糖尿病の合併症③腎臓障害
最終的に太い血管までやられた場合は、腎臓が障害されます。
腎臓は尿を出すことで水分や老廃物を外に出す機能があります。そのため症状としては、
- むくむ
- タンパクなどの栄養成分が漏出する
- 老廃物が体内を回りやすくなり、疲れや嘔吐が出現する
などの症状があります。
あまりに機能が低下してしまうと、透析をせざるを得なくなってしまいます。
糖尿病の命に関わる合併症
糖尿病は初期の段階であればどの臓器も改善できます。ですがが病状が進行すると、糖尿病をコントロールしたとしても元に戻れなくなってしまいます。
先ほどの例でいっても、
- 神経が鈍麻することで足の先が腐ってしまう
- 視力障害が重篤化して失明してしまう
- 腎機能が改善できず透析になってしまう
など、重症化すると糖尿病の治療を開始しても、時すでに遅しになってしまいます。
また元に戻れなくなるのは、他の臓器も同じです。特に糖尿病は神経・眼・腎臓以外の全ての血管にダメージを与え、動脈硬化を引き起こします。
動脈硬化が進行すると、
- 心筋梗塞
- 脳梗塞
- 脳出血
など心臓や脳に致命的なダメージを与える病気が出現します。
これらの病気は発症すると命の危険性もある恐ろしい病気です。さらには糖尿病は、神経障害によって痛みの感覚が鈍ってしまうことも多く、そのため発見が遅れてしまうことがあります。
そのため糖尿病は、症状が重症化する前に治療しなければならない病気になります。
糖尿病の検査と診断の流れ
糖尿病は、
- 空腹時血糖値
- 随時血糖値
- HbA1c
の3つの数値から診断する値です。
おそらく普通の健康診断の結果だと、
- 血糖値
- HbA1c
しか出ていないかと思います。
血糖値とは、血液中の糖分の量をあらわしています。そのため、食事に影響されやすい数値でもあります。健康診断などでは朝食を抜くことが多く、空腹時血糖が図られています。病院などで予期せずに血糖値を測定する方は、食事は気にしないでとっているために随時血糖値となります。
HbA1c(ヘモグロビン エーワンシーと呼びます)は、食事に影響することなく過去1~2か月間の血糖値の平均値に反映される数値です。ヘモグロビンとは、我々の酸素を運ぶ赤血球の成分です。このヘモグロビンが糖分と結合している割合が、HbA1cとして示されるのです。
ですから随時血糖しか取れないときは、HbA1cも測定することで診断を考えていきます。
糖尿病の診断基準をチェック
次に、糖尿病と診断する診断基準をチェックしてみましょう。
糖尿病は、
- 早朝空腹時血糖値が126以上
- 随時血糖値(糖分負荷試験血糖値)が200以上
- HbA1cが6.5%以上
のどれかが当てはまると、糖尿病型と診断されます。
2016~2017年度の糖尿病のガイドラインは、以下のように示されています。

まず①か②の血糖値が当てはまり、かつ③のHbA1cが6.5%以上であれば糖尿病確定となります。
健康診断で採血された方は、一度自分の結果をみてみましょう。健康診断での血糖値は、先ほど記載したように空腹時血糖値として考えます。ですから血糖値126以上で、糖尿病疑いと記載されているかと思います。
血糖値だけでは糖尿病と確定はできず、
- HbA1cが6.5%以上
- 確実な糖尿病症状(口渇・多飲・多尿・体重減少)
- 糖尿病網膜症
があることで診断が確定します。
糖尿病再検査と境界型糖尿病の診断
例えば血糖値が200以上で、かつHbA1cが6.5%以上の方は、健康診断の結果の時点で糖尿病と診断されます。
そういった糖尿病が確定しなかった人も油断はできません。
- 随時血糖値が126以上から200未満でも、HbA1cが6.5%以上の人
- HbA1cが6.5%未満でも、血糖値が200以上の人
は黒と断定できなくても、白ともいえない灰色の方です。
そのため、再検査を1か月以内にすることがガイドラインでは推奨されています。先ほどもお伝えしましたが、①では糖尿病の症状があれば確定診断もできます。ですが、なかなか症状だけでは分かりづらいと思います。
ですから健康診断などで糖尿病が疑われた方は、再検査をお勧めしています。当院では、糖尿病の診断に必要な
- 血糖値
- HbA1c
が院内で10分程度で測定できます。採血してから後日受診する煩わしさがなく、すぐに結果をみて評価をすることができます。
この血糖値とHbA1cで糖尿病と確定できなかった場合も、安心はできません。一度糖尿病が疑われた方は、ガイドラインでは3~6か月以内に血糖値を再度測定することが求められます。
特に空腹時血糖値と負荷後2時間血糖値の値によっては、正常と糖尿病の境界型の糖尿病の方もいます。
境界型糖尿病の基準は、以下のようになっています。


負荷後2時間血糖値は、糖分を摂取した2時間後の値です。
- 空腹時血糖値が110~126
- 負荷後2時間血糖値が140~200
のどこか1つの項目が当てはまると、糖尿病境界型と診断されます。
この糖尿病境界型は、徐々に糖尿病を発症していくことも考えられます。ですから糖尿病境界型と診断された方も、定期的に血糖値およびHbA1cを測定した方がよいと考えられています。
そのため当院では、境界型糖尿病の方も可能であれば3か月後の再検査をご提案しています。
糖尿病は基準値に当てはまったらアウト、当てはまらかったらセーフという病気ではありません。少しでも糖尿病の素因がある方は悪化しないように、定期的に確認するようにしましょう。
糖尿病診断後に必要となる検査
糖尿病と診断された方は、早く血糖値を下げて糖尿病を治療したいという思いが先行するかと思います。ですが糖尿病の方は、まずは全身の状態を確認することをお勧めしています。
糖尿病は血糖値やHbA1cという数字で重症度が分かるため、つい数字を下げることに目が行きがちです。
しかし糖尿病を治療する目的は、血管障害による症状とその進行を防ぐことにあります。数字を下げるのはあくまで過程であって、最終目標ではありません。
そのため当院では、糖尿病と診断された方は全身の精査をお勧めしています。具体的には、
- 一般項目の採血
- CPR(C-ペプチド)の測定
- 尿検査
- 頚部、腹部エコー
などをお勧めしています。①から③は、ほぼ必須の検査です。
特に糖尿病の方は、
- 過食
- アルコール過剰摂取
- 運動不足
- 肥満
などの方が多いです。糖尿病の症状の一つに動脈硬化の進行が挙げられます。動脈硬化を進行する他の要因として、
- 脂質異常症
- 高血圧
- 肥満(メタボリックシンドローム)
が挙げられます。糖尿病と合わせてこの4つの疾患を死の四重奏と呼び、4つ揃うと非常に動脈硬化の可能性が高くなります。これらの4つの病気は1つだけの疾患を持っている可能性は低く、複数持ち合わせていることが多いです。
もし複数の因子がある方は、血糖値だけ一生懸命下げても動脈硬化を食い止めることができません。そのため、採血などによって生活習慣病を広く調べることが重要です。
上記疾患以外にも糖尿病の方は、
- 脂肪肝などの肝障害
- 糖尿病による腎機能障害
- 暴飲暴食による電解質異常
など様々な病気が隠れていることがあるため、一般項目を含めて広く採血していきます。
また、可能であればC-ペプチド(CPR)を一緒に測定します。CPRとは、我々の膵臓が分泌しているインスリン量の指標になります。
インスリン分泌量が極端に低い場合は、最初に説明したインスリン分泌能が破壊された1型糖尿病の可能性があります。その場合は総合病院での治療が望ましいため、ご紹介させていただくこともあります。
一方でCPRが極端に高い場合は、インスリンが大量に出ているのにも関わらず、インスリンの抵抗性が非常に高くて効きづらくなっていることを示しています。そのためインスリン量の分泌を促すようなお薬を投与しても、あまり効果がありません。
このようにCPRを測定することで、
- 糖尿病のタイプ
- 糖尿病の重症度
- 糖尿病の治療薬の選択
など幅広いことが確認できます。
また調べるのは採血だけではなく、尿も重要です。糖尿病という名前のように、尿から糖分が実際にどれくらい出ているのかを見ておくことが、重症度の確認になります。
微量アルブミンは、たんぱく質のひとつになります。実は糖尿病の方は、糖分が糸球体という濾過処理する部位を通過し続けることで、網目が大きくなっていき濾過する能力がどんどん低下する特徴があります。
穴が大きくなると、本来であれば体に必要な物質であるタンパク質なども、尿に漏れ出てしまうようになるのです。そのためこの微量アルブミンがすでに出ているかどうか、もし出ているとしたらどれくらい漏れ出ているかで、糖尿病による腎障害が確認できます。
そして最後にエコー検査です。まず頚部のエコーですが、これは動脈硬化の具合を確認できます。糖尿病を治療する最大目標は、この動脈硬化を防ぐことにあります。そのため動脈硬化がすでにある方、それも非常に進行している方は、動脈硬化の治療を優先する必要があります。
その動脈硬化がどれくらい進んでいるのか確認するのに最も良いのが、首の血管です。首の血管は、脳と体の血液が行き来する非常に重要な血管になります。その部位が動脈硬化が進行して詰まりやすくなっていると、脳梗塞や脳出血のリスクが非常に上昇します。
次に腹部エコーは、我々が見ただけではわからない体内の臓器を確認できます。糖尿病の方は、臓器にも様々な障害が起きていることがあります。
腹部エコーによって、
- 胆石
- 脂肪肝
- 糖尿病膵
- 消化管不全麻痺
- 神経因性膀胱
などの数多くのことが分かります。人によっては
- 肝臓癌
- 膵臓癌
などの癌が隠れていることもあります。もし癌が隠れている場合は、早期発見・早期治療が大原則になるため、腹部エコーをすることによって一命を取り留めた人も大勢います。
エコーは超音波検査のため、全く痛みなどの侵襲性を伴いません。また当院はエコー検査専門の技師にやってもらうため、非常に正確に診断することができます。
この他にも糖尿病は、全身に影響を与える疾患です。病状を確認しながら人によっては、
- 胸部レントゲン
- 心電図
- 眼科へ併診(4階の眼科と連携)
など柔軟に対応していきます。
糖尿病と診断された方は、いかに血糖値を減らすかの前に、まずは糖尿病でどれくらい体の中で障害が起きているか確認してみましょう。
高血糖と低血糖、どちらが問題?
糖尿病の症状・合併症、検査、診断についてお話してきましたが、最後の治療に入る前にお伝えしておきたいことがあります。
みなさんは高血糖と低血糖状態、どちらが問題と思いますか?糖尿病の方は血糖値が低ければ低いほどよいと考えている人も多いですが、これは大間違いです。
糖分とは、我々の体内のエネルギー源です。特にぶどう糖は、脳が働くための大切な栄養となります。どんな数値も高すぎても低すぎても問題になりますが、血糖値の場合は低血糖の方が非常に大きな問題になります。
高血糖すぎでも糖尿病ケトアシドーシスといって、
- 嘔吐
- 腹痛
- 意識障害
などの重症な症状が出ることもあります。ですが大部分が、糖尿病の治療をしていない方です。
一方で糖尿病治療中の方でよく起きるのが、低血糖症状です。
- 空腹感
- 発汗
- ふるえ
- 動悸
- だるさ
- イライラ感
などが初発症状としてあり、重度になると脳への糖分が足りなくなり意識を失って倒れてしまいます。
高血糖と違い低血糖は、糖尿病の方が
- 病気で食事量が低下した
- インスリン注射後に忙しくて食事が食べれなかった
- 血糖値を下げようと薬剤を過剰投与した
などですぐに引き起こされてしまいます。特に血糖値を直接下げるインスリン注射を導入されている方は、低血糖が起きた際にすぐに対応できるように、一緒にぶどう糖も処方されることも多いです。
そもそも糖尿病の治療の大原則が、
- 食事療法(カロリー摂取量を減らす)
- 運動療法(カロリー消費量を増やす)
になります。そのため糖尿病は薬で血糖値を下げれば良いと安易に治療すると、非常に危険です。
低血糖症状を起こさないためにも、
- 医師から指示された薬の量を厳守する
- 体調が悪くて食事量が減った場合など注意する
- 低血糖症状について知っておく
ことが糖尿病の治療では大切になります。
糖尿病の薬物治療について
糖尿病のガイドラインでは、治療の目標値をHbA1cで定めています。
- 血糖正常化を目指す場合:6.0未満
- 合併症予防のための目標:7.0未満
- 治療強化が困難な人の目標:8.0未満
を目指すように記載しています。最初は食事療法・運動療法を施行したうえで、それでも改善がない方の場合、内服薬が適応されます。
糖尿病は国民病のため、非常に多くのお薬が登場しています。2017年の糖尿病のガイドラインでも、
①インスリン抵抗を改善する薬剤
- ビグアナイド薬(肝臓での糖代謝の抑制)
- チアゾリジン薬(骨格筋・肝臓でのインスリン感受性の改善)
②インスリンの分泌を促進する薬剤
- DPP-4阻害薬(血糖依存のインスリン分泌促進)
- グリニド薬(食後の高血糖に対する速やかなインスリン分泌促進)
- スルホニル尿素薬(インスリン分泌の促進)
③糖分の排出および吸収阻害薬
- α―グルコシダーゼ阻害薬(炭水化物の吸収を阻害)
- SGLT-2阻害薬(腎臓でのぶどう糖排出促進)
の3種類のタイプに分けられています。
本来であれば、ガイドラインに準じて治療を開始します。しかし糖尿病のガイドラインは、「患者さんの症状、血糖値の状態、合併症などを加味し治療を開始する」としか記載されておらず、どのお薬から始めたら良いかは決まりがありません。
ここで今までの検査結果が役に立ちます。特にCPRで体内のインスリン量がどれくらい分泌しているか確認するのは、治療方針を決定するために重要です。
インスリンがすでに大量に分泌されているにも関わらず血糖値が高い方は、インスリンの抵抗性が強いことを示しています。このように方に、②のインスリンの分泌を促進する薬剤を選択しても、あまり効果が期待できません。
すでにインスリンが体内で大量に分泌されている方は、①のインスリン抵抗を改善する薬剤や、③の糖分の排出および吸収阻害薬を組み合わせて血糖値を低下させます。
一方で、低血糖症状になり過ぎないように注意することが必要です。特にインスリンを分泌を促す薬剤でスルホニル尿素薬は、血糖値が下がりやすいお薬として有名です。
スルホニル尿素薬は内服すると24時間効果が持続するため、場合によっては低血糖状態が続いてしまう危険性があります。
このように、お薬のそれぞれの利点・欠点を把握したうえで患者さんによって使い分けないと、効果がないばかりが、逆に低血糖症状など危険な状態にさらしてしまうのが糖尿病治療の怖さです。
さらに糖尿病のお薬は、一つの種類でも複数の会社から数多く発売されています。例えばDPP-4阻害薬では、
- グラクティブ
- ジャヌビア
- エクア
- ネシーナ
- トラゼンタ
- スイニー
- オングリザ
- ザファテック
- マリゼブ
の9種類ものお薬が登場しています。同じDPP-4阻害薬でも、
- トラゼンタは腎機能の状態に関係なく処方できる
- ジャヌビアは9種類の中でも価格が安い
- ザファテックやマリゼブは週1回内服で治療が可能
などなど各々の特徴があります。
特に糖尿病のお薬の登場は日進月歩で、毎年たくさんの新しいお薬が登場します。昔からあるお薬でもよいこともあれば、新しいお薬の方が良いこともあります。
糖尿病の教育入院とは?
上記で示した内服薬を組み合わせても血糖値のコントロールできない方は、本来であれば一度大きな病院で入院が必要になります。
糖尿病の合併症を全身評価して、糖尿病のことを理解して行くことが目的となるため、教育入院といわれます。内服薬で効果が得られない場合は、インスリン注射で血糖値を下げる必要があります。
高血糖がひどくなってしまうと、糖毒性といってインスリンがますます効きにくくなるという悪循環があります。インスリン注射でその悪循環を断ち切る必要があります。
しかし、どのくらいの量を投与すればどれくらい下がるかを確認しながらインスリン量を決定する必要があるため、入院下での導入が推奨されています。そのうえで糖尿病教育入院では、運動療法や食事療法について詳しく指導を受けていただきます。
糖尿病の治療は薬だけではなく、運動療法・食事療法が大切です。多くの方はこのことを理解していても、
- どのくらい食事量を制限すべきなのか?
- 何を食べた方が良いか?
- 運動はどのくらい行うべきなのか?
具体的にわからないことが多いです。また分かっていても、
- 付き合いでついつい食べてしまう
- 食事以外楽しみがない
- 運動する時間がない
といった形で、どうしても怠ってしまいがちです。
しかし内服薬でも血糖値をコントロールができない人は、このまま運動療法と食事療法に目を背けたまま治療するのは非常に危険です。
食事療法と運動療法に興味がある方は、脂質異常症のページに記載してありますのでご参照ください。
一方で知識として糖尿病を理解している患者様も、実際に糖尿病教育入院でしっかりと勉強し直した方が良いことが多いです。特に食事に関してはカロリー制限が必要になりますが、実際にどの食事がどれくらいのカロリーか実感がわかない人がほとんどだと思います。
入院して糖尿病食を実際に食べてみることで、本来の食事量がどれくらいであるべきか再認識できます。
糖尿病の注射治療、GLP-1受容体作動薬
教育入院が適切な患者さんの中には、
- 仕事が忙しくて入院なんてする暇がない
- 入院費用など、経済的に厳しい
といった方もいらっしゃるかと思います。
当院では患者様の社会背景を考えて、現実的な治療を提案させていただきます。話し合ったうえで入院に強い抵抗がある場合、当院ではGLP-1作動薬の注射を提案させていただくことがあります。
GLP-1作動薬は膵臓のGLP-1受容体に作用することで、体内の血糖値の状態に合わせてインスリンの分泌を促進する作用があるお薬です。GLP-1作動薬のメリットしては、
- 体内の血糖状態に合わせて作用するため、低血糖をきたす可能性が低い
- 投与量が患者さんによって使い分ける必要がない
- 食欲抑制作用がある
- 体重低下の作用がある
- 空腹時、食後の両方の血糖値を下げる
などが挙げられます。特に①の低血糖をきたす可能性が低い点は、非常にメリットが高いです。
インスリン注射は、投与することで直接血糖値を低下させる効果があります。そのため、どのくらいの量を投与すれば良いか、入院で細かく調整するべき治療です。インスリン注射の投与量が多すぎると低血糖を起こしてしまうからです。
一方でGLP-1作動薬は、低血糖の心配が少ないです。全ての患者様に同じ投与量となっており、調整が不要です。そして安全性も高いため、外来で通いながら導入することが可能な注射薬です。
このGLP-1作動薬は、
- ビクトーザ
- バイエッタ
- リキスミア
- ビデュヒュリオン
- トルリシティ
がありますが、当院では⑤のトルリシティを推奨しています。
その理由としては、
- 週1回の投与で対応可能
- 針の取り付けや取り外しが必要なし
- 食前や食後などを気にせず投与可能
- 薬液をふって混和する必要なし
と他と比べてメリットが大きいからです。特に①の週1回で投与可能な利点は、非常に大きいです。
注射は痛みを伴うので、毎日ではなく週1回の方が当然良いとは思いますが、痛みの点だけではありません。保険診療では注射の治療を導入した場合、「在宅自己注射指導管理料」が費用としてかかります。その際、
- 月に28回以上の注射回数・・・750点(3割負担で2,250円)
- 月に27回以下の注射回数・・・650点(3割負担で1,950円)
と、注射を投与する回数によって費用が変わります。
毎日投与すると月28回以上超えてしまいますが、週に1回であれば月に4~5回の注射で済むため、費用も安くなります。
現状としては、
- ビデュヒュリオン
- トルリシティ
の2剤が週に1回の投与が可能な注射薬です。
一方で週に1回では忘れてしまうので、毎日注射したいという方もいらっしゃいます。毎日投与する注射も処方可能ですので、ご希望があれば医師に相談してみてください。
糖尿病のインスリン注射治療について
インスリンとは、私たちの膵臓から分泌されているホルモンです。血糖値を下げるホルモンです。通常は以下の図のように分泌されています。

このように普通の方は、食事をして血糖値が上がったのを感じ取った時のみに、インスリンが分泌されます。しかし糖尿病の方では体内で生成されるインスリンだけでは足りないため、インスリンを人工的に追加します。これがインスリン注射です。
インスリン注射にも色々あります。
- 持続型(24時間効果をマイルドに持続して全体の血糖値を下げる)
- 即効型(食後など急激に血糖値の上昇に対して、早く血糖値を下げる)
- 中間型・混合型(持続型と即効型を混合することで、効果を持続しつつ、食後の血糖値も下げます)
このように、主に3種類があります。それぞれについて解説しましょう。
持続型インスリン注射
まず持続型インスリン注射を見ていきましょう。24時間持続することで、血糖値の全体を下げる注射薬になります。イメージとしては下記の図のようになります。

ただし血糖値は、食事の影響を受けて1日の中でも変動が激しいです。そのため24時間持続するインスリン注射は、基本的には効果がマイルドになります。効果が強すぎると、頻回に低血糖になってしまうからです。
ですから持続インスリン注射は、基本的に血糖値が最も低い状態の時の数値をみて投与量を決定していきます。我々が血糖値が最も低くなるタイミングは、朝起きて朝食前の血糖値です。夕食後から朝食前までが何も食べない時間が最も長いからです。
そのため持続インスリン注射は、この朝食前の最も絶食時間が長かった数値をみて、投与量を決定していきます。朝食前の血糖値よりも低くなることは、3食を規則的とっている方の場合はほとんどありません。そのため朝食前の血糖値は、最も重要な値です。
この朝食前の血糖値が高い方は、食後はさらに高くなることが予想されます。このため、持続型インスリンを投与する必要があります。
持続型インスリンは、
- ランタス
- トレシーバ
- レベミル
- インスリン、グラギニン(ジェネリック医薬品)
などがあります。
即効型インスリン注射
次に即効型インスリンです。
持続型血糖値で全体の安定を図っても、食後どうしても血糖値が上がってしまう方は多いです。そのため食後の血糖値を抑えるために、即効型インスリンを追加投与します。
イメージとしては、下記の図のようになります。

このように、持続型だけでは補いきれない食後の高血糖を即効型インスリンで抑えます。
即効型インスリンとしては、
- ヒューマログ
- ノボラピッド
- アピドラ
- ヒューマリンR
- ノボリンR
などがあります。
即効性インスリンは、実際の血糖値の変動をみながら調整をしていきます。即効性インスリンを投与する方は、毎食前に血糖値を測定します。
それぞれの血糖値をどのように見ていくかというと、
- 昼食前の高血糖:朝食の影響で高血糖
- 夕食前の高血糖:昼食の影響で高血糖
- 寝る前の高血糖:夕食の高血糖
このように考えます。ですから、
- 昼食前の高血糖:朝食前のインスリン量を増やす
- 夕食前の高血糖:昼食前のインスリン量を増やす
- 寝る前の高血糖:夕食後のインスリン量を増やす
という形になります。昼食前に高血糖だと、その後投与するインスリン量を増やしたくなるかと思います。
しかし昼食前に投与するインスリンを増やすのではなく、朝食前に投与したインスリンの効果が不十分だったと判断して、次回から朝食前のインスリン量を増やすようにします。
中間型・混合型インスリン
持続型と即効型を組み合わせた治療を、強化インスリン療法といいます。持続型でベースラインを整えて、即効型で細やかに調整をしていきます。それによって血糖値の変動を少しでも抑えていきます。
ですがこの強化インスリン療法では、自分で血糖値をこまめに測定しながらインスリンを頻回に投与することが必要です。良好な血糖コントロールが目指せますが、負担が大きくはなります。
本来であれば強化インスリン療法が良いのですが、患者様の社会状況や、食事の都度針は刺したくないなどの希望がどうしても強い場合は、中間型や混合型のインスリン注射を考慮します。
- 中間型インスリン・・・作用が持続型ほど長くは続かないが、即効型より長く続く注射。持続効果は12-24時間ほど
- 混合型インスリン・・・持続型もしくは中間型と即効型を混合した注射
です。
中間型や混合型の効果のイメージとしては、

このように中間型や混合型インスリン注射は効果が持続し、かつ投与直後にすぐに効果を認めるため、持続型および即効性の両方の効果を持っています。
中間型は混合型に比べて、投与後のインスリン効果がやや緩やかという違いがありますが、ほぼ同じイメージでまずは良いと思います。ただし両方の効果を持つということは、小回りが効かないというデメリットにもなります。
前述したように、糖尿病は低血糖を起こさないようにインスリン治療を行うことが大前提になります。そのため、小回りが効かない中間型や混合型のインスリン製剤は、あまり量を増やすことができません。
食後の高血糖を抑えようと大量に投与することはできませんので、インスリン治療の中でも軽症の患者様に限られます。
中間型インスリンとしては、
- ノボリンN
- ヒューマリンN
などが挙げられます。
また、混合型インスリンとしては、
- ヒューマリンログミックス
- ノボラピッドミックス
- ノボリンR
- イノレットR
などがあります。
インスリン注射をされている方は、自分がどのような注射を投与しているか一度見直してみるのも良いかもしれません。
さらにインスリンを投与する方は、
- インスリン針
- アルコール綿
- 自己測定器
が必要になると思います。
上記3つは当院では院内で処方させていただきます。近隣の総合病院が良く使用している
- ナノパスニードルⅡ 34G(テルモ)
- BDマイクロファインプラス 32G、31G(ベクトン・ディッキンソン)
- ペンニードル 32G(ノボ・ノルディクス)※( )内は発売会社です。
上記3種類を用意しています。
また自己測定器は、
- ニプロケアファストR A30(ニプロ)
- ニプロトゥルーピコブルー A30(ニプロ)
- ニプロフリースタイルフリーダムライト A30(ニプロ)
- アキュチェックアビバ ナノ(ロシュダイアグノスティックス)
- メディセーフ(テルモ)
- グルテストNeo(アークレイ・三和化学)
- グルコカードG ブラック(アークレイ)
- ワンタッチべリオ(ジョンソン&ジョンソン)
を準備しております。
もちろんこれ以外でも柔軟に対応できるため、上記以外のをお使いの方は事前にご連絡いただければと思います。
インスリン注射は理解が不十分なままに使っていると、非常に危険なお薬です。
- 自分のインスリンの注射はどんな効果があるのか?
- インスリン注射はいつまで続けなければいけないのか?
- 体調が悪くなった時にインスリン注射の投与量をどうすれば良いか?
分からないことがあれば医師にご相談ください。
【お願い】
「こころみ医学の内容」や「病状のご相談」等に関しましては、クリニックへのお電話によるお問合せは承っておりません。
診察をご希望の方は、受診される前のお願いをお読みください。
【お読みいただいた方へ】
医療法人社団こころみは、東京・神奈川でクリニックを運営しています。
「家族や友達を紹介できる医療」を大切にし、社会課題の解決を意識した事業展開をしています。
医療職はもちろんのこと、法人運営スタッフ(医療経験を問わない総合職)も随時募集しています。
(医)こころみ採用HP取材や記事転載のご依頼は、最下部にあります問い合わせフォームよりお願いします。

執筆者紹介
大澤 亮太
医療法人社団こころみ理事長/株式会社こころみらい代表医師
日本精神神経学会
精神保健指定医/日本医師会認定産業医/日本医師会認定健康スポーツ医/認知症サポート医/コンサータ登録医/日本精神神経学会rTMS実施者講習会修了
カテゴリー:糖尿病 投稿日:2019-05-11
関連記事

糖尿病で足にでる症状は?しびれ・痛み・壊疽などについて解説
糖尿病で足にでる症状は?しびれ・痛み・壊疽などについて解説 糖尿病は進行すると、足に症状が出てくることがあります。 それはどのような症状なのでしょうか? 本記事では、糖尿病でみられる足の指のしびれるような痛み、足のつり、… 続きを読む 糖尿病で足にでる症状は?しびれ・痛み・壊疽などについて解説
カテゴリー:糖尿病 投稿日:
人気記事

【医師が解説】喘息の長期管理薬(吸入ステロイド)の効果と副作用
喘息の長期管理薬とは? 喘息は、気道に慢性炎症が起きて狭くなっている状態です。それが引き金となって気道が過敏になり、ちょっとしたきっかけで咳や息苦しさをくり返します。 喘息の治療は、 炎症を抑え、喘息の悪化や発作を予防す… 続きを読む 【医師が解説】喘息の長期管理薬(吸入ステロイド)の効果と副作用
カテゴリー:喘息の長期管理薬(吸入ステロイド) 投稿日: