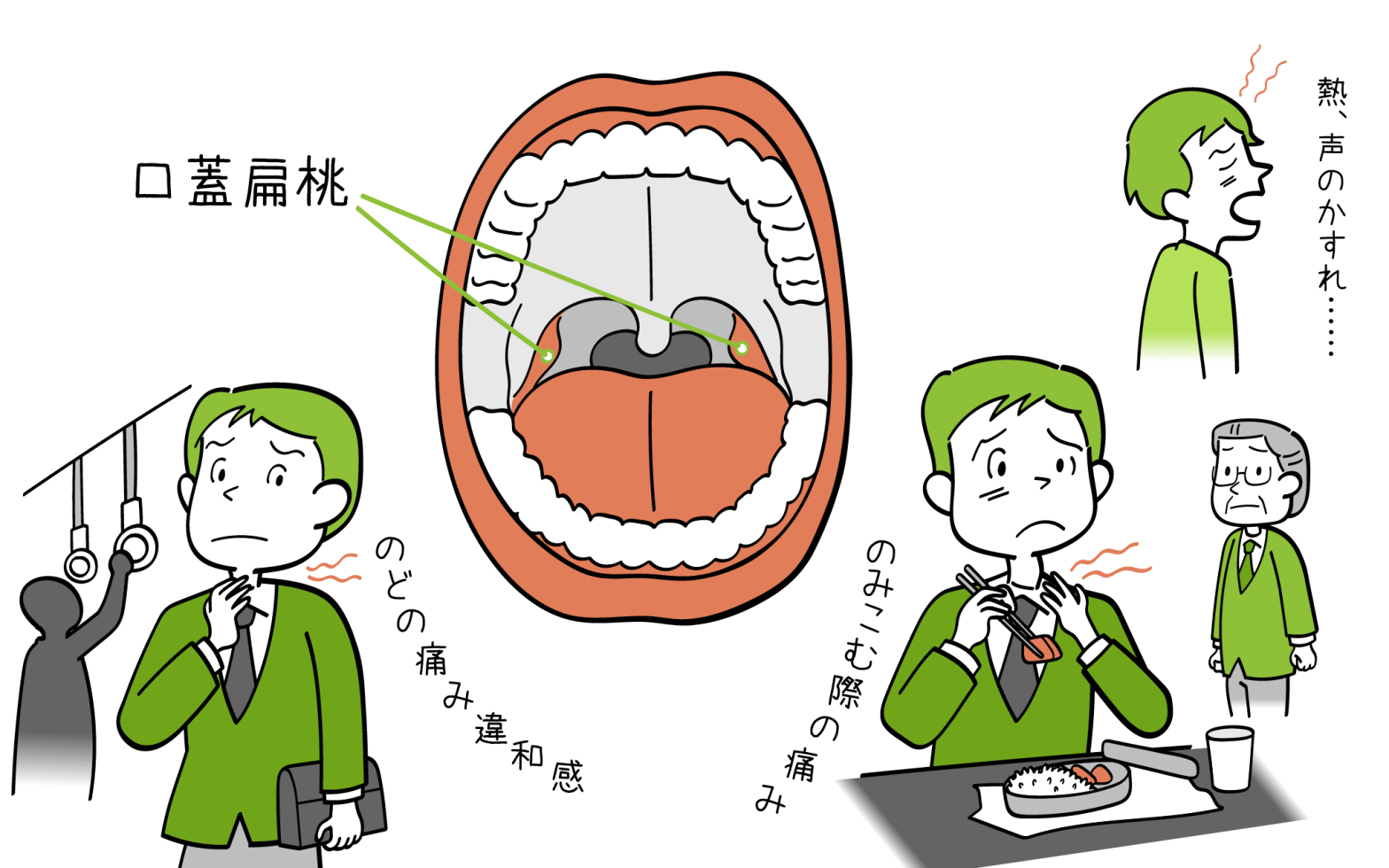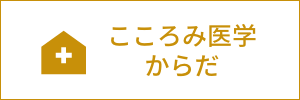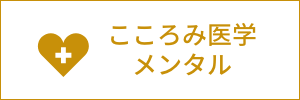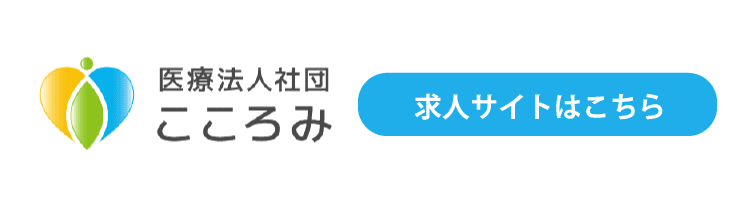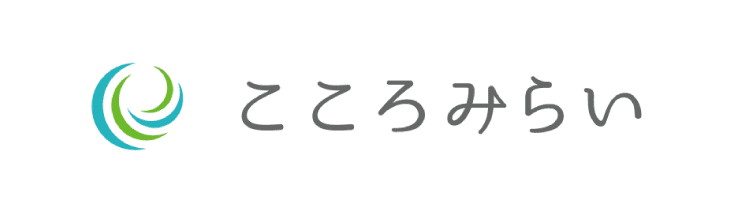慢性疲労症候群の治療には、漢方薬を使うことも
慢性疲労症候群とは、これまで健康で普通に生活していた方が、急に強い倦怠感におそわれてしまう病気です。
頭痛や微熱といった自律神経症状と共に、疲労感や脱力感などが長きにわたって続くのですが、その背景には様々な身体の機能的異常があることがわかってきています。
しかしながら、根本的に改善する治療法は今のところありません。対症療法によって治療をすすめていきます。
このような慢性疲労症候群の治療に、漢方が有効なことがあります。ここでは、慢性疲労症候群にはどのような漢方が向いているのか、お伝えしていきたいと思います。
漢方での慢性疲労症候群の考え方
漢方においては、
- 身体に必要なエネルギー(気)や栄養(血)が体の隅々まで回らないこと
が慢性疲労の原因と考えます。そして、慢性疲労症候群は気血そのものが不足した「虚」の状態ととらえ、治療を行っていきます。
また、疲労を考えるときには「脾」の機能低下も考慮します。漢方で脾は、胃とともに消化に重要な働きをしているとされています。この脾や胃の機能が低下すると、エネルギーとなる栄養が不足して全身に運べなくなり、スタミナ不足から慢性的な疲労状態となってしまいます。
慢性疲労症候群で使われる漢方薬
それでは、慢性疲労症候群の治療で使う具体的な漢方薬をみてみましょう。1つ注意点としては、漢方は体質・病態・原因など、個人個人に合わせた「証」をみながら選ぶ必要があります。合わない漢方薬はかえって身体の負担となりますので、飲むときは医師と相談してください。
(※「証」について詳しくは、『漢方の「証」について』をお読みください)
| 漢方薬 | 適応症例 |
|---|---|
| 補中益気湯(陰・虚) | 気を補う場合の基本 |
| 四物湯(陰・虚) | 血を補う場合 |
| 加味帰脾湯(陰・虚) | 消化不良があり不安や不眠が強い場合 |
| 十全大補湯(陰・虚) | 貧血気味で気血を補う場合 |
| 人参養栄湯(陰・虚) | 十全大補湯でも不十分な場合 |
慢性疲労症候群では、気虚や血虚を補う必要があります。そのためには、補気剤や補血剤と呼ばれる漢方薬を使っていきます。
補中益気湯(ほちゅうえきとう)
補気剤の中でも効果が強く、気虚の基本的な処方といわれているのが補中益気湯です。
「中」は漢方で腹部=胃腸のことを意味して、消化機能を丈夫にして気を補います。血の不足が少ない若い人で使うことが多い漢方薬です。
四物湯(しもつとう)
栄養が不足していて疲れがたまっている場合、補血剤の基本的な処方である四物湯を用います。疲れて動悸がする場合などは、よい適応です。主に高齢または虚弱で栄養状態が不良な方に用います。
加味帰脾湯(かみきひとう)
不眠や抑うつ気分などが強く消化不良を認める場合は、加味帰脾湯を用います。心脾両虚(気力や体力の源が足りなくなってしまい、心と脾が活動できなくなっている状態)に有効と言われています。
十全大補湯(じゅうぜんたいほとう)
消耗が著しく、補気と補血の両方が必要になる場合は、十全大補湯を用います。十全とは完璧という意味で、失われた気も血も完璧に補うことを意味します。全身機能を高めて代謝を促進し、疲労感を軽減します。
人参養栄湯(にんじんようえいとう)
十全大補湯でも効果がなかった場合、十全大補湯に生薬を加えた人参養栄湯を用います。
まとめ
漢方においては、慢性疲労の原因を「エネルギーや栄養が足りなくなってしまう気虚・血虚」「消化機能が低下する脾虚」と考え、それらを補う補気剤や補血剤を中心に使っていきます。
同じ病気であっても、患者さんごとの体質などをみながら選ぶことが大切です。
【お願い】
「こころみ医学の内容」や「病状のご相談」等に関しましては、クリニックへのお電話によるお問合せは承っておりません。
診察をご希望の方は、受診される前のお願いをお読みください。
【お読みいただいた方へ】
医療法人社団こころみは、東京・神奈川でクリニックを運営しています。
「家族や友達を紹介できる医療」を大切にし、社会課題の解決を意識した事業展開をしています。
医療職はもちろんのこと、法人運営スタッフ(医療経験を問わない総合職)も随時募集しています。
(医)こころみ採用HP取材や記事転載のご依頼は、最下部にあります問い合わせフォームよりお願いします。

執筆者紹介
大澤 亮太
医療法人社団こころみ理事長/株式会社こころみらい代表医師
日本精神神経学会
精神保健指定医/日本医師会認定産業医/日本医師会認定健康スポーツ医/認知症サポート医/コンサータ登録医/日本精神神経学会rTMS実施者講習会修了
カテゴリー:慢性疲労症候群 投稿日:2020-08-12
関連記事
人気記事

【医師が解説】喘息の長期管理薬(吸入ステロイド)の効果と副作用
喘息の長期管理薬とは? 喘息は、気道に慢性炎症が起きて狭くなっている状態です。それが引き金となって気道が過敏になり、ちょっとしたきっかけで咳や息苦しさをくり返します。 喘息の治療は、 炎症を抑え、喘息の悪化や発作を予防す… 続きを読む 【医師が解説】喘息の長期管理薬(吸入ステロイド)の効果と副作用
カテゴリー:喘息の長期管理薬(吸入ステロイド) 投稿日: