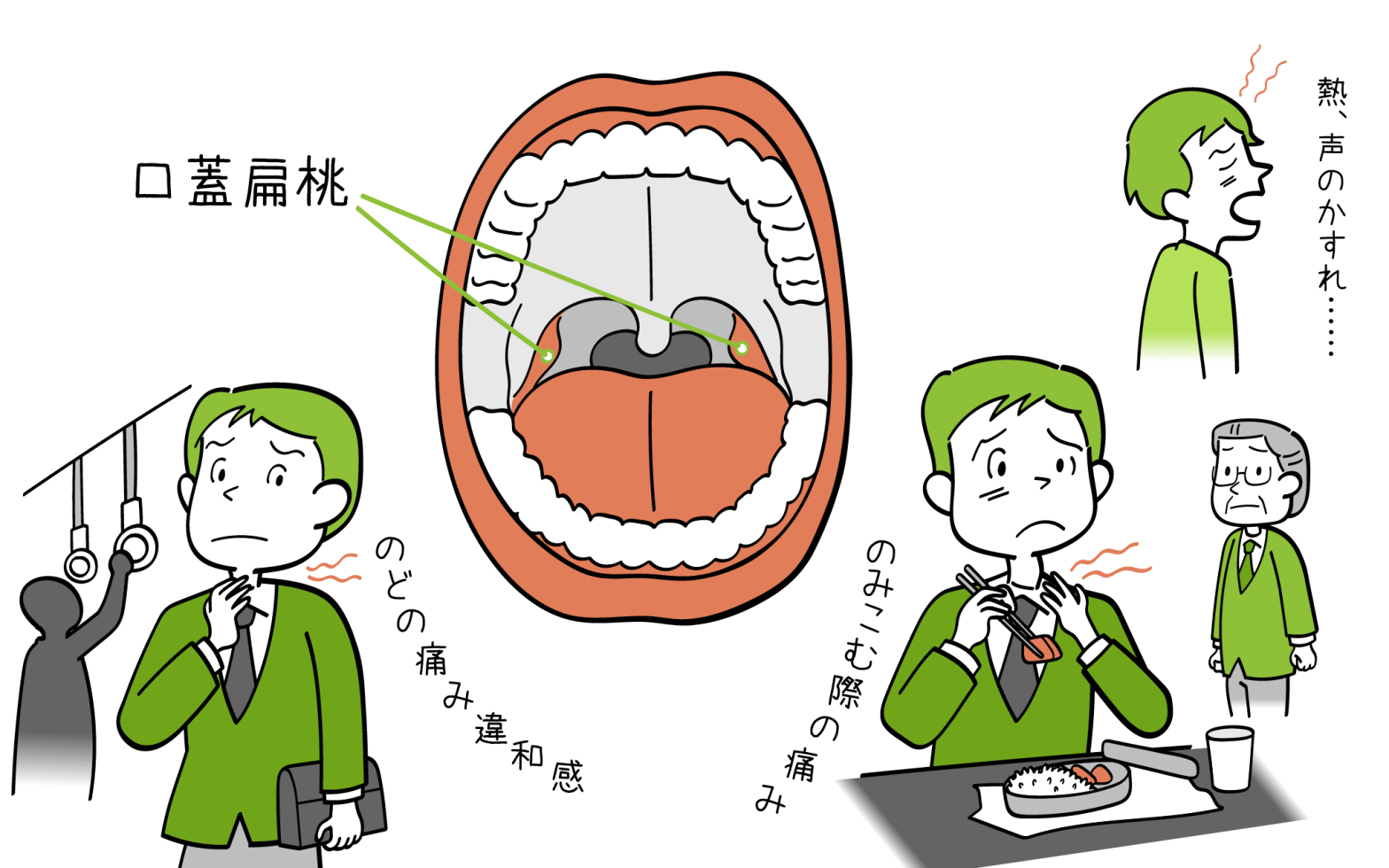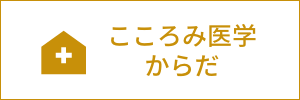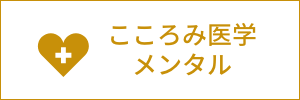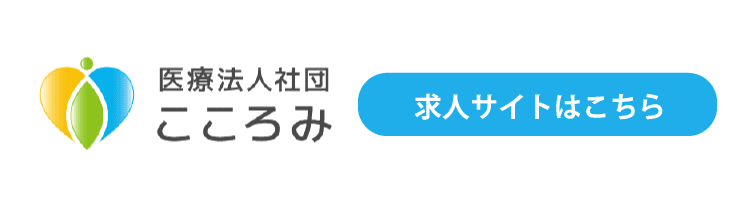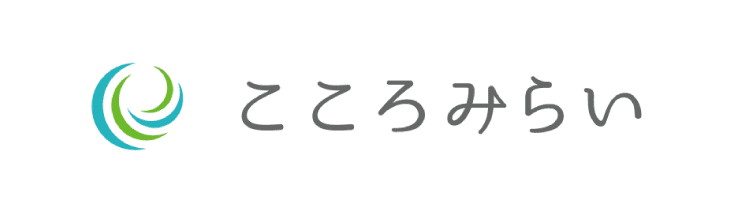はじめに
睡眠時無呼吸症候群の治療では、口腔内装置(マウスピース)や持続陽圧呼吸装置(CPAP)が主に用いられます。
しかし、CPAPは症状が中等度から重度の患者さんにしか使えません。
そのため、CPAPを使った方が良いようにみえるけれど、検査結果だけを見れば中等度の診断にもならない、という症例もあります。
一方、CPAPはマスクを装着するために眠れない、使いたくないという患者さんも多くおられます。
このように口腔内装置やCPAPを使ってみたけれど治療効果が得にくいという方々への他の治療法として、今回は手術で気道を拡げることについて説明します。
下顎の形と気道の関係
喉仏の上のあたりを触ってみてください。
そこには馬蹄形(U字形)をした舌骨という骨があります。
一方、顎の先端をオトガイといいます。
このオトガイと舌骨の間にオトガイ舌骨筋という筋肉があります。飲み込みの時に舌骨を前に引く筋肉です。
舌はほぼ全てが筋肉でできています。その足場の1つもオトガイです。
オトガイから舌に広がるオトガイ舌筋という筋肉が、舌を前に出す動きをします。
寝ている間に気道が狭くなる理由は、これらオトガイ舌骨筋やオトガイ舌筋がリラックスするため、舌骨や舌そのものが落ち込むため、気道が狭くなります。
顎の大きさについて
顎は上顎、下顎、それぞれ幼少期から高校生の時期にかけて成長発育していきます。
この時に上下の顎が協調しながら成長発育すればいいのですが、上下顎ともに前方に過成長した場合もあれば、上顎が前方に発育した場合(出っ歯)、下顎が前に出た場合(受け口)、下顎が小さい場合(小下顎症・鳥貌)など、様々なパターンがあります。
また指しゃぶりを長くやめられなかったような場合は、噛み合わせた時に奥歯しか噛み合わない状況(開咬)になる方もおられます。
これらの症例では、上下の歯並び、かみ合わせの調整が必要になってきます。
歯並びの調整は歯列矯正治療となりますが、抜歯もしくは非抜歯で歯を並べるだけでは噛み合わせを作ることが非常に困難なことがあります。
この場合は歯を動かすだけでなく、歯を支える骨の形の調整も必要になってきます。これを顎変形症といいます。
顎変形症の治療
顎変形症の診断は、矯正歯科医が行います。
様々な検査をして顎変形症と診断されると、外科矯正手術(顎矯正手術)と、その手術前と後の歯列矯正が必要と判断されます。
そして、これら全てが保険診療として治療を受けることができます(2023年1月現在)。
注意しないといけないのは、しっかり咬めない状況に対してかみ合わせを整えることが目的の治療であり、美容が目的ではありません。
例えば「顎のエラを削ってほしい」はかみ合わせをと直接の関係が無いため、自費診療になります。
顎変形症を診断するにはレントゲン、CT画像、石膏模型などを用いて、分析します。
その分析結果から、上顎と下顎をどの方向にどれだけ移動させ、歯をどう並べるべきかという治療計画を決定します。
治療計画を患者さんに説明し、了解が得られたら、まず術前矯正治療を行います。
術前矯正では、手術によってほぼ噛み合うような歯並びを目指します。平均して1年半程度かかります。
上顎に対してはLe Fort1(ルフォーワン)骨切り術という方法がよく用いられ、下顎に対しては下顎枝矢状分割術やオトガイ形成術がよく用いられます。
大まかな内容としては、まずLe Fort1骨切り術を行なって上顎のかみ合わせの位置を調整し、プレートで固定します。
当初はステンレスワイヤーやチタンプレートしかありませんでしたが、最近は強度の面で吸収性プレートが用いられるようになりました。
プレートで固定後、上顎に合うよう下顎も切って(下顎枝矢状分割術など)移動させ、プレートで固定する、という流れです。
さらに、嚥下のことを考慮して、オトガイの位置も前方に出す手術(オトガイ形成術)も合わせて行うことがあります。
全てお口の中で行う手術ですので、顔の表面にはほとんど傷はつきません。
入院・手術の費用は窓口負担3割の方でおよそ36万円(2023年2月現在)ですが、限度額認定、医療費控除などの対象になりますので、詳しくは病院の会計窓口でご相談ください。
外科矯正手術で気道が拡がる
このかみ合わせを作る、という目的で上顎と下顎、オトガイ部を前方や上方に移動させると、オトガイ舌骨筋により舌骨が前方に引かれた位置へと移動します。
またオトガイ舌筋により、舌の後方(舌根部)も前方に移動しますので、気道が広くなります。
かみ合わせを作ることで咀しゃくしやすくなるだけでなく、気道も拡がり、呼吸がしやすくなるという効果もあります。
睡眠時無呼吸症候群でかつ歯並び・かみ合わせが気になる方は、一度医師・歯科医師に相談してみましょう。
この外科矯正手術が有効な治療法かもしれません。
参考文献
- 大鶴 光信ら. Current Opinion 睡眠時無呼吸症候群の治療 CPAP以外の治療. 呼吸と循環 2008; 56(7): 737-740.
- 津田緩子.【1からおさらい 睡眠時無呼吸症候群の治療とケア】(Theme 2)有効な治療法はあるの? 口腔内装置の使用や口腔外科領域の手術療法. 呼吸器ケア 2014; 12(11): 1132-1134.
- 西島嗣生ら.【睡眠時無呼吸症候群】睡眠時無呼吸症候群の治療 閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)におけるCPAP以外の治療. 日本内科学会雑誌 2020; 109(6): 1082-1088.
【お願い】
「こころみ医学の内容」や「病状のご相談」等に関しましては、クリニックへのお電話によるお問合せは承っておりません。
診察をご希望の方は、受診される前のお願いをお読みください。
【お読みいただいた方へ】
医療法人社団こころみは、東京・神奈川でクリニックを運営しています。
「家族や友達を紹介できる医療」を大切にし、社会課題の解決を意識した事業展開をしています。
医療職はもちろんのこと、法人運営スタッフ(医療経験を問わない総合職)も随時募集しています。
(医)こころみ採用HP取材や記事転載のご依頼は、最下部にあります問い合わせフォームよりお願いします。

執筆者紹介
大澤 亮太
医療法人社団こころみ理事長/株式会社こころみらい代表医師
日本精神神経学会
精神保健指定医/日本医師会認定産業医/日本医師会認定健康スポーツ医/認知症サポート医/コンサータ登録医/日本精神神経学会rTMS実施者講習会修了
カテゴリー:睡眠時無呼吸症候群(SAS) 投稿日:2023-03-10
関連記事
人気記事

【医師が解説】喘息の長期管理薬(吸入ステロイド)の効果と副作用
喘息の長期管理薬とは? 喘息は、気道に慢性炎症が起きて狭くなっている状態です。それが引き金となって気道が過敏になり、ちょっとしたきっかけで咳や息苦しさをくり返します。 喘息の治療は、 炎症を抑え、喘息の悪化や発作を予防す… 続きを読む 【医師が解説】喘息の長期管理薬(吸入ステロイド)の効果と副作用
カテゴリー:喘息の長期管理薬(吸入ステロイド) 投稿日: